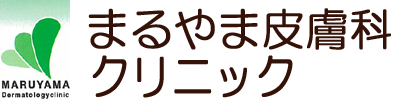当院ではよりよい治療手段の確立に貢献するため、積極的に新薬の臨床試験に取り組んでおります。
新しいお薬や新しい治療方法にご興味のある方はご相談ください。



皮膚疾患に悩む患者さんに寄り添った診療を行います
皮膚疾患に悩む患者さんに寄り添った診療を行います
お知らせ
今後も定期的にさまざまな情報を更新してまいりますので、ぜひご覧ください。
2023年4月よりマイナンバーカードによるオンライン資格確認システムの運用を開始いたしました。
受付に設置したカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、ご本人の顔認証もしくは暗証番号を用いてログインすることで健康保険の情報だけでなく、処方された薬剤の内容、特定健診の検査結果、病院での手術履歴などさまざまな診療情報を当院での診療に役立てることが可能となります。
また当院のカードリーダーでは自治体が発行する医療券や公費負担認定証などの読み取りにも対応しています。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前に利用登録をする必要がありますが、利用登録の申請が済んでいない方でも当院のカードリーダーを利用するとその場で利用申請をおこなって、すぐに保険証として利用することができるようになります。
この度厚生労働省より通達のあった診療報酬改定を受け、2023年4月1日より、初診料算定時に下記の加算を追加いたします。
(以下の点数は2023年4月~12月末の間の特例措置となります。)
*マイナンバーカードの提示による初診の受付をされた場合:2点
*従来の保険証などで初診の受付をされた場合:6点
金曜日午後、土曜日は加藤卓朗医師・院長丸山の2名で診察を行いますので、順番が早く進みます。
- 非接触型の体温計の設置
- 常に玄関ドア、窓を開けての換気
- 空気清浄機の設置
- アルコール消毒(非接触型)の設置
- 1日2回以上の清掃
- スタッフ全員、コロナ予防接種3回接種済み
N95マスク、フェイスガードの着用
診療カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
午前休診
午後休診
休診日
診療案内
医師紹介

院長 丸山 隆児
2006年4月に当院を開業いたしました。
早いもので、2023年4月で17年が経過いたしました。
皮膚疾患でお悩みのことがございましたら当院へご相談ください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
医院案内

医院名まるやま皮膚科クリニック
診療科目皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、アレルギー科
住所〒136-0074
東京都江東区東砂7-19-13
ベルコモン南砂301
TEL03-5632-2077
FAX03-5632-2077
休診木曜・土曜午後・日曜祝日
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50~12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 14:50~18:30 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
交通案内
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線「南砂町駅」2a出口より徒歩9分(エレベーター・エスカレーター利用の方は2b出口をご利用ください) |
|---|---|
| 最寄バス停 | 東陽町駅より都営バス亀21 南砂六丁目下車徒歩5分 亀戸駅より都営バス亀23 南砂五丁目団地下車徒歩5分 錦糸町駅より都営バス両28 東砂四丁目下車徒歩5分 大島駅より都営バス亀21 東砂四丁目下車徒歩5分 西大島駅より都営バス両28、亀29 東砂四丁目下車徒歩5分 葛西駅より都営バス秋26 東砂六丁目下車徒歩6分 |
院長の想い

皮膚の疾患で悩んでいる方へ
皮膚は全身の表面を覆うたいへん大きなひとつの臓器です。皮膚の状態にはその方の内臓の状況、精神状態、生活環境や生活習慣まで、その人の全人格が現れてきます。そうして頭、顔、手足など衣服で覆われていない部分の皮膚は、他人の資格に常に曝されています。そのために健やかな、健全な皮膚はその人全体を輝かせますし、反対に病気に罹った皮膚はその人にとって大きな苦痛の種となります。